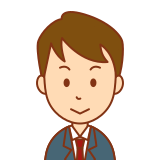
基本データ
本人情報
- 生年月日: 1985-01-01
- 性別: 男性
- 住所(都道府県): 東京
職業・収入関連
- 雇用形態: 正社員
- 勤務先での勤続年数: 10
- 職種: 製造
- 年収: 500
家族構成
配偶者の有無: あり
- 生年月日: 1990-01-01
- 性別: 女性
他扶養家族
扶養家族1: 関係: , 生年月日: , 性別:
居住形態
- 持ち家か賃貸か: 賃貸
- 住宅ローンの有無: なし
- 居住年数: 10
資産・負債状況
- 金融資産: 500
- 負債: 0
お金に関する価値観
保守的です
上記の基本データに基づいて以下の質問に答えてください
近々子供が生まれます。
教育資金をどういう風に貯めれば良いかわかりません。
まずは学資保険について教えてください

学資保険とは?
学資保険は、お子さんの教育資金を計画的に準備するための貯蓄型の保険です。契約者(通常は親)が保険料を払い、お子さんの進学時期(小学校・中学校・高校・大学など)に合わせて給付金を受け取ることができます。
学資保険の特徴
- 貯蓄機能
- 満期まで保険料を払い続けると、支払った額以上の金額(返戻率)が戻ってくることがある。
- 銀行預金よりも利回りが高い商品がある。
- 保障機能
- 契約者(親)が万一死亡または高度障害状態になった場合、以後の保険料の支払いが免除され、満期時には予定通り給付金が受け取れる。
- 保険会社によっては、医療保障がつくものもある。
- 給付金の受取タイミング
- 一括(大学入学時)
- 分割(高校・大学進学時に分けて受け取る)
学資保険を選ぶポイント
- 返戻率(払った額に対して戻ってくる割合)
- 100%を超えるものを選ぶとお得。
- 保険料払い込み期間や給付金の受取方法によって変動。
- 保険料の支払い方法
- 月払いより年払いのほうが総額が安くなることが多い。
- 一括払いのほうが返戻率が高い傾向。
- 保障内容の確認
- 保険料の払い込み免除特約があるか。
- 医療保障や育英年金などが必要かどうか。
学資保険のメリット・デメリット
メリット
✅ 計画的に教育資金を準備できる
✅ 契約者が万一の際も資金が確保される
✅ 生命保険料控除の対象になり、節税効果がある
デメリット
❌ 途中解約すると元本割れする可能性がある
❌ インフレに弱い(将来の学費が上がると、準備金が足りなくなるリスク)
❌ 他の資産運用手段(NISA・iDeCo等)と比較すると運用効率が低いことがある
どう貯めるべきか?
学資保険だけでなく、貯蓄や投資も組み合わせるのがオススメです。
- 学資保険(安全資産) → 確実に貯めたい分
- ジュニアNISA(運用資産) → 長期的に増やす可能性
- 預金・定期積立(流動資産) → いつでも使える資金
特に保守的な価値観をお持ちなので、学資保険+預金+少額のジュニアNISA の組み合わせが良いでしょう。
次に、具体的な学資保険の選び方や、他の貯蓄方法について知りたいことはありますか?
“”” 《ディスクレーマー》
AI chat Robot ロボFPはchatGPTをベースとしたカスタムGPTsです。その回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は専門家に確認するようにしてください。
専門家のご紹介(アフィリエイト広告を含む)
また、本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任において利用されますようお願いします。
“””
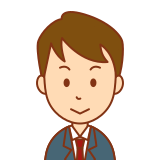
ジュニアNISAは廃止されたと聞きましたが

はい、おっしゃるとおり、ジュニアNISAは2023年で新規の制度としては終了しました。ただし、既に開設済みの口座は2024年以降も引き続き運用可能で、2024年以降は払い出し制限が撤廃されるため、より柔軟に資金を引き出せるようになりました。
ジュニアNISAの代わりに使える制度
ジュニアNISAが終了したため、今後の教育資金の運用方法として以下の選択肢を考えるとよいでしょう。
1. 新NISA(2024年開始)を活用する
- 特徴
- 2024年から始まる「新NISA」では、親が自分の名義で投資を行い、将来教育資金として使うことが可能。
- 年間投資枠:つみたて投資枠(120万円)と成長投資枠(240万円)があり、合計最大360万円/年の非課税投資が可能。
- 生涯投資枠:1,800万円(うち成長投資枠1,200万円まで)。
- 教育資金に向いている理由
✅ 途中で売却しても制約がない(必要なタイミングで引き出せる)
✅ 長期運用でリターンを期待できる
✅ 投資対象の自由度が高い(投資信託・ETF・個別株など)
2. つみたてNISA(2023年までの制度)を活用する(※新NISAと統合)
- 2023年以前に「つみたてNISA」を利用していた場合は、引き続き運用可能。
- 2024年以降は、新NISAに移行して継続投資するのが良い選択肢。
3. 教育資金専用の預金や定期積立を活用する
- 学資保険と併用する形で預金を確保するのも有効
- 児童手当をそのまま貯めるのも一つの手段
**4. iDeCo(個人型確定拠出年金)**は教育資金には向かない
- 60歳まで引き出せないため、教育資金としては不向き
- ただし、親の老後資金としては有効
まとめ:どの方法を選ぶべき?
お金に関する価値観が「保守的」とのことなので、安全性と運用性のバランスを考えて、
✅ 学資保険(確実に貯める)
✅ 新NISA(運用しながら増やす)
✅ 預金(流動性を確保)
の3つを組み合わせるのがベストです。
教育資金の具体的な積み立て例(目安)
目標額:大学進学時に300万円〜500万円
- 学資保険:毎月15,000円〜20,000円(確実に貯める)
- 新NISA:毎月20,000円〜30,000円(長期運用)
- 預金:児童手当を全額貯金(約15,000円/月)
このように分散することで、リスクを抑えながら教育資金を確保できます。
もっと詳しく知りたいポイントがあれば、お知らせください!
“”” 《ディスクレーマー》
AI chat Robot ロボFPはchatGPTをベースとしたカスタムGPTsです。その回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は専門家に確認するようにしてください。
専門家のご紹介(アフィリエイト広告を含む)
また、本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任において利用されますようお願いします。
“””

コメント
廃止されたジュニアNISAをしれ〜と勧めてきたのは明らかに誤りですね!
ロボFPの欠点として直近に制度変更があると弱いことがわかります。
この辺は改良の余地がありそうですね。