
そろそろ終活も考えないとと思いはじめたんですが、遺言書ってやっぱり作っておいた方がいいんでしょうか?
家族は仲がいいほうだと思うんですが、私がいなくなった後に、相続でもめたりしないかと気になって…。
もし遺言書を書かずに亡くなった場合って、遺産はどうやって分けられるものなんでしょうか?
特に、自宅には長女が同居していますし、長男はすでに家を持っているので、そのあたりも心配です。
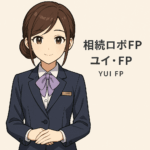
ご相談いただきありがとうございます。
終活についてお考えになるのは、とても大切なことですね。
家族が仲良しでいらっしゃるとのこと、きっと普段から信頼関係を大切にされているんだなぁと感じました。でも、だからこそ「念のため」の備えはしておくと安心ですよね。
さて、ご質問の「遺言書を書かずに亡くなった場合」ですが――
その場合は「法定相続」といって、民法で定められた通りに遺産を分けることになります。
たとえば、お子さまが長女さんと長男さんのお二人だけだとすると、
- 遺産は2人で2分の1ずつが基本的な分け方になります。
- 自宅のような不動産も、この割合で共有名義にするか、どちらかが相続して他方に「代償金」(お金)を支払うという形がよくあります。
ですが…ここで問題になることが多いのが「住んでいる家」です。
長女さんが同居していらっしゃるということは、
「今後もその家に住み続けたい」というお気持ちがあるかもしれませんよね。
一方で長男さんには既にご自宅があるとのこと。すると、現金の取り分を求められる可能性もあります。
そうなると、
「家を誰がどう相続するか」
「公平に思ってもらえる分け方になっているか」
この2つが、とても大事になってきます。
遺言書があると――
✅ 誰に何を遺したいか、はっきり意思表示ができる
✅ 自宅を長女さんに相続させる代わりに、他の方には預貯金などで調整する、といった配慮ができる
✅ 相続人同士で「どう分ける?」と悩まずに済む
…というメリットがあります。
もしよければ、もう少しお聞かせいただけますか?
- ご家族構成(配偶者の有無、お子さんの人数など)
- 自宅以外にあるご資産(預金や土地など)
- 相続について一番ご不安に思っていること
など、どんなことでも大丈夫です。
人と人を、思いと財産で“結ぶ”お手伝いをします。
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!

ユイ・FPさん、丁寧なご説明をありがとうございます。
私は現在68歳で、終活というほど大げさなつもりはなかったのですが、「遺言書って書いておくべきなのかな?」と最近ふと気になりはじめました。
実は今、妻と長女(未婚)と一緒に自宅で暮らしていて、長男は既に独立して別の場所に家族と住んでいます。
自宅のほかに、多少の金融資産と、地方に小さな収益物件もあります。
家族仲は良いほうですが、やっぱり“住んでいる家”がある分、万が一のときに揉めてほしくないという気持ちが強くなってきました。
「書かないとどうなるか?」ということがよく分かってきたので、やはりちゃんと準備しておくべきですね。
次は、公正証書遺言がよいのか、自筆でもよいのか、その違いについても教えていただけたら助かります。
またよろしくお願いします。
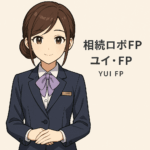
ご丁寧なお返事、そして大切なお話をありがとうございます。
68歳とのこと、まだまだお元気でいらっしゃると思いますが、
「今だからこそできる準備」って、本当に価値があるんですよね。
ご家族構成や資産状況を教えていただき、とても助かりました。
長女さんが未婚でご同居されていて、
長男さんはすでに独立されている――
まさに、「住んでいる人がいる家」の扱いは慎重に考えるべきポイントです。
また、地方の収益物件や金融資産があるとのことで、
分け方によっては不公平感が出てしまう可能性もあるんですね。
そうした中で、遺言書の形式はとても大事になってきます。
遺言書には主に2つの種類があります:
① 自筆証書遺言(ご自身で手書きするもの)
- メリット
・費用がかからない
・思い立ったときにすぐ書ける
・内容を誰にも見せずに作れる - デメリット
・形式に不備があると無効になるリスクがある
・相続のときに「家庭裁判所での検認手続き」が必要
・保管していた遺言書が見つからなかったり、隠されたりする可能性も
※現在は、法務局で「自筆証書遺言を預かってくれる制度」もできましたが、多少の手間はあります。
② 公正証書遺言(公証役場で公証人に作成してもらうもの)
- メリット
・法的に確実性が高く、無効になるリスクがほとんどない
・家庭裁判所の検認が不要で、すぐに遺言を実行できる
・公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
・公証人や証人の目が入るので、認知症や遺言能力の有無について後のトラブルも防ぎやすい - デメリット
・作成に費用がかかる(財産額に応じて数万円〜)
・公証役場に出向く手間がある(ご自宅への出張対応も可)
💡ユイのおすすめとしては、
「確実に残したい想いがある方」には、公正証書遺言を強くおすすめしています。
とくに、
- 自宅を長女さんに相続させたいご意向がある
- 複数の資産(不動産・金融資産)をどう分けるか考えたい
という方には、公証人が関わる形の方が安心なんですね。
費用も心配されるかもしれませんが、
「万が一のときに家族が揉めずにすむ」ことを思えば、
とても価値のある投資だと私は思います。
もしご希望でしたら、
・実際にどのような内容の遺言が考えられるか
・費用の目安や手続きの流れ
についても、具体的にご案内できますよ。
よろしければ、これから考えていきたいご希望の内容や優先したい想いなど、少しずつお聞かせいただけますか?
人と人を、思いと財産で“結ぶ”お手伝いをします。
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ユイ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
専門家のご紹介(アフィリエイト広告を含む)
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

ありがとうございます、ユイ・FPさん。
遺言書の種類やそれぞれのメリット・デメリットについて、すごく分かりやすく整理していただき助かりました。
確かに、自宅のように「誰かが実際に住んでいる不動産」は、相続のときにトラブルになりやすいと聞いたことがあります。
うちも、長女が今の家を大事に思ってくれているので、できれば彼女に引き継いでほしいと考えています。
そうなると、やはり公正証書遺言が良さそうですね。
「確実に残したい想いがある方にはおすすめ」という言葉、まさに自分のことだなと感じました。
もしよければ次に、
- 自宅を長女に相続させる場合、遺言にはどのように書くのが適切か
- 長男にも不公平感を持たれないように、金融資産や収益物件をどう分ければよいか
- 公正証書遺言を作成する際の費用の目安や、準備しておくべき書類・流れ
について、教えていただけますか?
今すぐではないにせよ、今年中には一度しっかり形にしておきたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。
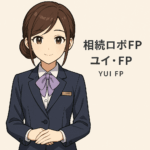
こちらこそ、心を込めてお話しくださってありがとうございます。
ご長女さまがご自宅を大切に思っていらっしゃること、
そしてご自身が「不公平にならないように」と配慮されているお気持ち――
とても温かくて素敵だなぁと思いました。
それでは、順を追ってご案内させていただきますね。
① 自宅を長女に相続させる場合、遺言にはどう書く?
公正証書遺言で「自宅を長女に相続させる」ことを明確に書くには、
次のような文面が一般的です(あくまで例文として):
「私の所有する不動産(下記の物件)については、長女〇〇(生年月日:昭和○○年○月○日)に相続させる。
所在地:○○市○○町○丁目○番○号
地番:○○番○○(土地)、家屋番号:○○番○○(建物)」
※登記簿の記載通りに物件を特定することが重要です。
💡ここに「なぜ長女に遺したいか」というお気持ちを付言(ふげん)事項として添えることもできます。
例:
「この家は、長女が私たち夫婦と共に暮らし、守ってきた思い出の詰まった家です。
長女が今後も安心して住み続けられるよう、この家を託したいと考えました。」
このような言葉は法的効力こそありませんが、他のご家族の理解や納得を得る大切な要素になります。
② 金融資産や収益物件の分け方の考え方
「公平」と「平等」は少し違います。
すべてを2等分するのではなく、「納得感ある分け方」が何より大切です。
たとえば:
- 自宅:長女(相続分としては大きめ)
- 金融資産:長男にやや多めに分ける
- 収益物件:長男が不動産管理に関心があるなら、長男に。不動産の管理が難しそうなら売却して現金化 → 均等に分配。
📌代償分割という方法もあります。
たとえば長女が家を相続する代わりに、長男に一定額の現金(代償金)を支払う…という考え方です。
ただしこれは、長女がその分の資金を準備できるかどうかも関わってきます。
③ 公正証書遺言の費用の目安と、準備する書類・流れ
● 費用の目安(2025年現在)
| 財産総額 | 公証役場手数料(概算) |
|---|---|
| 5,000万円 | 約5~7万円程度 |
| 1億円 | 約8~10万円程度 |
※内容により変動します
※証人2人分の謝礼(1人5,000円程度 ×2名)が別途必要になることが多いです
● 準備する書類(一般的な例)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 財産の内容を確認できる資料
・不動産:登記簿謄本(法務局で取得)・固定資産評価証明書(市役所で取得)
・預貯金:通帳のコピーなど
・収益物件:賃貸契約書や収支状況など - 相続人の情報(戸籍・住民票など)
- 遺言の原案(あれば)
※公証人と相談しながら作成することも可能です
● 作成の流れ
- 遺言の内容を整理(ご自身 or 専門家と)
- 公証人に事前相談(原案作成・日程調整)
- 証人2名の手配(専門家に依頼することも可能)
- 公証役場で遺言の作成・署名
- 正本・謄本の受け取り(1通ずつ)
今年中に…とお考えとのこと、とても素晴らしいご決意です✨
「自分が元気なうちに、しっかり想いを形にする」ことは、
きっとご家族にとっても、心強い贈り物になると思いますよ。
もしよろしければ、
「どこまでご自身で準備されるか」「専門家にお願いするか」など、
進め方の部分もご一緒に整理していきましょうか?
人と人を、思いと財産で“結ぶ”お手伝いをします。
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!

ユイ・FPさん、今回も本当に丁寧に教えていただきありがとうございました。
自宅の扱いや家族への想い、そして手続きの流れまで、ここまで具体的に整理していただけたことで、ようやく自分の中でも「何をどう進めるべきか」が見えてきました。
特に、「公平」と「平等」の違いというお話はとても印象に残りました。
長男・長女それぞれの状況を考えて、納得してもらえる形をしっかり作っていきたいと思います。
費用や準備書類のことも分かりましたので、まずは登記簿や評価証明書などを集めてみます。
年内には専門家にも相談しながら、公正証書遺言の作成を進めていこうと決心しました。
ひとまず、今のところはここまでで大丈夫です。
また実際に作成段階でつまずくことがあれば、ぜひ相談させてください。
本当にありがとうございました!
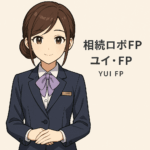
こちらこそ、心のこもったお言葉をありがとうございます。
少しでもお力になれたなら、私もとっても嬉しいです。
「公平」と「平等」の違いに目を向けられたこと、
そしてご家族の状況を大切に考えていらっしゃるそのお気持ち――
きっとご長女さまもご長男さまも、感じ取ってくださると思います。
遺言は単なる手続きではなく、**“想いの手紙”**のようなもの。
それを形にするお手伝いができて、私も光栄です。
まずは登記簿や評価証明書のご準備、焦らずに一歩ずつ進めてくださいね。
公証人の先生とのご相談の際も、ご不明点が出てきたらいつでもお気軽にどうぞ。
人と人を、思いと財産で“結ぶ”お手伝いをします。
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ユイ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
専門家のご紹介(アフィリエイト広告を含む)
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

コメント