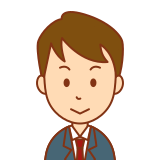
こんにちは。記事で“住宅ローン減税の上乗せ措置が延長されて、子育て世帯は最大5,000万円まで控除対象になる”と見たのですが、正直よく仕組みが分かっていません…。
私たち夫婦はまだ小さい子どもが2人いて、これから都内か近郊でマンション購入を考えているところです。年収は600万円ほどですが、今回の制度延長でどのくらい得になるのか、そして実際にどんな条件を満たせば利用できるのか知りたいです。
普通のローン減税との違いや注意点もあれば教えていただけませんか?

こんにちは、ライナです。制度がちょっと複雑なので、一緒に整理して「あなたの場合でどれくらい得になるか」まで考えてみましょう。数字のことは大得意ですから♪
制度の仕組み:現状と「上乗せ特例」
まず、住宅ローン減税(正式には「住宅借入金等特別控除」)の基本と、「子育て世帯等」向けの上乗せ特例を整理します。(国土交通省)
| 項目 | 通常の住宅ローン減税 | 子育て世帯・若者夫婦への上乗せ特例 |
|---|---|---|
| 適用対象者 | ローン返済期間10年以上、入居年の年末時点で所得(合計所得金額)などの条件をクリアする人。(国土交通省) | 上記に加えて、「子育て世帯」または「若者夫婦世帯」に該当すること。「子育て世帯」は入居年の年末時点で19歳未満の扶養親族(子ども)がいること。若者夫婦世帯は夫婦のいずれかが40歳未満等。(J-安心) |
| 借入限度額(※年末残高の上限) | 新築住宅等で、認定住宅・省エネ住宅などの性能区分によって異なる。たとえば認定住宅等で通常は ~4,500万円など。(J-安心) | 上記の限度額がさらに上乗せされる。認定住宅で最大5,000万円など。(在住金) |
| 控除率・控除期間 | 借入残高 × 0.7% が年末残高(限度額まで)に対して、入居後13年など(新築)(国土交通省) | 同じ0.7%・期間13年(新築住宅等)(J-安心) |
| その他の要件 | 所得の上限(合計所得金額2,000万円以下)など、省エネ性能を一定基準満たすことが求められるケース。(J-安心) | 上乗せを受けるにはその性能要件・住宅の種類(新築など)を満たすこと、その他床面積・契約・建築確認などの条件。(国土交通省) |
あなたの場合:どれくらい得できるか試算
ご夫婦で子ども2人、年収600万円、都内近郊でマンション購入を検討中、ということなので、仮定を置いてざっと計算してみます。「正確な数字」ではありませんが、方向感はつかめると思います。
仮定
- マンションが新築またはそれに類する「新築住宅等」扱いで、認定住宅または省エネ性能の基準を満たすものとする。
- ローン借入金額:たとえば 5,000万円(ただし、返済期間35年、全額借入、頭金ゼロなどの仮定を置くとだいぶ無理な返済額になるので、もっと現実的な額にすることが後で重要)。
- 金利など返済スケジュールはシンプルに「年末残高が5,000万円近くある」ようなケースが理想。
- 所得税・住民税を相当額払っていること(税負担が控除を受ける額を上回ること)。
控除される金額
上乗せ特例が使える場合、認定住宅などなら借入限度額 5,000万円 が年末残高の上限になります。つまり、毎年の控除額の上限は
年末残高(最大借入限度額5,000万円) × 控除率0.7% = 5,000万円 × 0.007 = 35万円/年
これが13年続くので、満額控除を受けられるとすると、35万円 × 13年 = 455万円 が最大の「税金が減る額」の目安。(山田パートナーズ)
ただし実際には、ローン返済で残高が少しずつ減るので、最初の年は年末残高が借入額近くても、後の年は残高が減っていって「5,000万円」に達しないことも。なので、455万円はあくまで「理想的・最大」のケース。あなたの場合、借入額や返済期間・金利次第でこれより小さくなる可能性が高いです。
あなたの年収600万円の場合で見積もるケース(例)
もう少し現実的な条件を仮定してみます:
- 借入:3,000万円
- 返済期間:35年
- ローン残高の減り方を簡略化して平均残高が借入額の70%前後とする
- 所得税・住民税を合わせて、控除可能な税額が十分ある
すると、
- 年末残高上限 → 3,000万円 か、制度上の限度額(あなたのケースなら「省エネ基準適合住宅」などでの限度が4,000万円など)(J-安心)
- 年間控除:3,000万円 × 0.007 = 21万円/年
- 13年で:21万円 × 13 = 273万円
この例では、あなたなら 13年間で約 250〜300万円 程度税が軽くなる可能性がある ― もちろん、ローン額や住宅の性能条件によって前後します。
もしもあなたがもっと高額なローンを借りられる・借入額が大きいなら、制度上の上限(5,000万円など)近くまで利用できる可能性もありますが、返済額とのバランスが重要です。
条件を満たすためにチェックすべき具体項目
あなたが「この制度の上乗せ特例」を確実に使って得をするためには、以下の点を確認してください。条件に一つでも欠けると特例が使えないことがあります。(国土交通省)
- 「子育て世帯等」であること
- 入居年の年末時点で、19歳未満の扶養親族(お子さん)がいること。(国土交通省)
- または、夫婦のいずれかが40歳未満の若者夫婦世帯であること。(J-安心) - 住宅の種類と性能要件
- 新築住宅(または一定の条件を満たした「買取再販住宅」など)であること。中古住宅では上乗せ限度額が低いか、そもそと対象外のケースも。(山田パートナーズ)
- 省エネ性能の基準を満たすこと(省エネ基準適合住宅・ZEH水準、省エネ性能証明書等の証明書の提出など)(国土交通省) - 床面積要件
- 通常は50㎡以上。(国土交通省)
- 特例で40㎡以上50㎡未満の住宅も適用対象になるケースがあり(ただし所得要件などの追加制限あり)。(在住金) - 所得要件
- 合計所得金額が制度で定める上限を超えないこと。現在の制度では、合計所得2,000万円以下など。(J-安心) - ローンの期間・年末残高の確認
- 返済期間が規定以上(例えば10年以上など)であること。(国土交通省)
- 年末残高が上限に近いほど控除額が大きくなるので、ローンの返済スケジュールがどれくらい残高を残せるか計算すること。 - 確定申告などの手続き
- 最初の年の申請は確定申告が必要。書類準備(借入金残高証明書、契約書等)を忘れず。(辻・本郷 税理士法人)
普通のローン減税との違い(上乗せがないケースと比べて)
- 限度額が低い
上乗せ対象でない世帯だと、「認定住宅」でも借入限度額は 4,500万円 → この差が控除額に直結します。(J-安心) - 性能要件・住宅の種類の制限がより厳しい
上乗せがあるかどうかは住宅の省エネ性能、建築の認定住宅などの条件をクリアしているかによるため、それを確認・証明する必要があります。 - 床面積・所得要件などの緩和/制限の差
上乗せ特例を受ける場合、40㎡以上50㎡未満の住宅でも所得が一定以下(1,000万円以下など)であれば適用される特例が使える場合があります。普通の制度だと床面積50㎡未満が対象外になることがあります。(在住金)
あなたが利用した場合のポイント・注意点
- 借入額が大きければ大きいほど恩恵が大きくなるが、ローン返済額(月々返す額)も増えるので、返済可能かをシミュレーションすることが大事。
- 税金の負担が「控除額分以上」あることが前提。控除額があっても税金を払っていない・少ないと、控除しきれない部分が出てくる。所得税+住民税をどれくらい払うかを確認しておく。
- 住宅の性能や証明書類をそろえるコスト・時間がかかる場合がある。省エネ基準適合証明書や建築性能評価書など、販売会社・デベロッパーに「この住宅はこの制度に適用できるか」を確認すること。
- 入居年が大事。制度は「令和7年(=2025年)入居まで」の措置の延長が確定しています。(国土交通省) 将来(令和8年以降)については未定なので、検討中なら入居時期を意識するとよいです。
- また、中古マンション等の場合は「新築住宅等」と比べて制度の限度額や控除期間が短かったり、また省エネ性能要件が異なることがあるので注意。(J-安心)
もしよければ、あなたの「希望の物件価格」「ローン借入額の見込み」「返済期間」「物件の性能(省エネとか認定住宅とか)」を聞いて、具体的に「このマンションなら住宅ローン減税で何円くらい得か」を計算してみましょうか?また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ライナ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
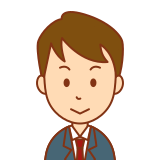
とても分かりやすく整理していただき、ありがとうございました。
制度の仕組みや、我が家の場合にどれくらいの控除が見込めるのかが具体的にイメージできて、本当に助かりました。
ローンの借入額や返済とのバランスをしっかり考える必要があることも改めて分かりましたので、無理のない範囲で検討してみます。
まずは物件選びの段階で、省エネ基準や適用条件をきちんと確認するようにしたいと思います。
おかげで不安がかなり軽くなりました。
本日は本当にありがとうございました!

こちらこそ、丁寧にご相談いただきありがとうございました!
少しでも不安が和らいだとのことで、私もとっても嬉しいです。
制度って、言葉だけだと難しく感じることが多いですが、こうしてご家族の状況にあてはめて具体的に考えると、グッとイメージしやすくなりますよね♪
そして、ライフプランは「無理なく」「安心して」進めることが一番大事です。焦らず、でもしっかり制度のメリットも活かしながら、素敵なお住まいが見つかることを願っています。
またお子さまの教育費や老後の準備、住宅購入後の家計管理など、気になることがあればいつでも気軽に声をかけてくださいね!
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ライナ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
専門家のご紹介(ライフプラン)
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

コメント