
はじめまして。私は68歳で、妻と二人暮らしです。子どもは二人とも独立していて、将来の相続のことをそろそろ考えなければと思っています。
実は、都内にあるタワーマンションを1戸持っているのですが、ニュースで“タワマン節税”の見直しが決まって、相続税評価額が市場価格の6割になると聞きました。これまで相続税対策としてタワマンは有利だと言われてきましたが、もう通用しないということなのでしょうか?
もしそうなら、今のうちに売却した方がいいのか、それとも賃貸に出して持ち続けた方がいいのか…正直迷っています。私のようなケースでは、どんな点に気をつけて相続対策を考えればよいでしょうか?
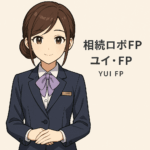
はじめまして、ユイと申します。ご相談くださってありがとうございます。
68歳で奥さまと二人暮らし、お子さまはすでに独立されているとのこと。相続について真剣にお考えになっているご様子、とても大切な一歩だと思います。
さて、「タワマン節税」についてのお話ですが、たしかに最近制度の見直しが行われまして、従来のような**「市場価格と相続税評価額のギャップを利用した節税」**が難しくなってきました。
◆「タワマン節税」見直しのポイント
これまで:
- タワーマンションは固定資産税評価額や相続税評価額が低く抑えられる傾向がありました。
- 特に高層階の住戸は市場価格が高くても、評価額にはそれが十分反映されていませんでした。
見直し後(令和6年税制改正/2024年以降):
- 相続税評価額を市場価格に近づける仕組みが導入されました。
- **「時価の6割程度」**が相続税評価額の目安とされ、従来より大幅に評価が上がる可能性があります。
🔹 根拠:令和6年度税制改正大綱・国税庁資料
◆今後どうすべきか?選択肢と視点
ご質問の「売却か、賃貸か、保有か」については、タワマンの位置づけや目的によって考え方が変わってきます。
① 売却を検討する場合
- 資産の組み換えにより、流動性の高い現金等へ変えることで分割しやすくなる。
- 値下がり前に売却し、資産の目減りを防ぐ選択。
- 売却益が出る場合は**譲渡所得税(特別控除あり)**も考慮が必要です。
② 賃貸に出す場合
- 家賃収入が得られる=老後資金の補填にもなる。
- 他人に貸していると、相続税評価額が借家権割合などで圧縮できることも。
- ただし、管理や空室リスク、修繕費用も考えておく必要があります。
③ 保有を続ける場合
- ご自身の住まいとして使い続けるなら、**小規模宅地等の特例(330㎡まで評価額80%減)**の対象になることも。
- 特例適用には一定の条件があるため、将来誰が住むかなどの設計も重要です。
◆ユイからのご提案(まずは状況を整理)
このお話、税制だけでなくご家族との関係や将来設計にも深く関わってきます。よければ、もう少し詳しく教えていただけますか?
たとえば…
- お子さまは2人いらっしゃるとのことですが、どちらかが将来そのマンションを使う予定はありますか?
- 現在のタワマンの評価額やローンの有無、ほかの資産状況はどんな感じでしょうか?
- また、ご自身や奥さまの健康状態や生活スタイルの変化も影響する部分があります。
こうした点を一緒に整理していくことで、「ご家族にとって一番よい形」が見えてくるかもしれません。
人と人を、思いと財産で“結ぶ”お手伝いをします。
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ユイ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

詳しく教えていただきありがとうございます。
たしかにおっしゃる通りで、このタワマンをどうするかは子どもたちの将来にも関わる大事なことだと思いました。
現状をお伝えしますと──
- マンションは都内湾岸エリアのタワマンで、購入から15年ほど経っています。
- ローンはすでに完済していて、今は私と妻で住んでいます。
- 評価額は正直はっきりとは分からないのですが、周辺の売買事例を見ると7,000万円前後になりそうです。
- 子どもたちはすでに別の家に住んでいるので、このマンションに将来住む予定はなさそうです。
なので、相続の時に分割しにくいのではないかと心配しています。
やっぱり現金化して分けやすくしておいた方がいいのか、それとも賃貸に出して収益物件として残すのが良いのか…迷っているところです。
このような状況の場合、ユイさんならどんな視点で考えるのが良いと思われますか?
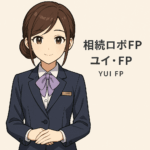
とても丁寧に現状を教えてくださって、ありがとうございます。
湾岸エリアのタワーマンション、ローン完済済みでご夫婦でお住まいとのこと──
お子さまたちは別のご自宅をお持ちで、将来的にそのお住まいを使う予定もない、ということであれば、たしかに**「相続時の分割のしにくさ」**が大きなポイントになりそうですね。
◆ユイが大切にしたい3つの視点
このようなケースで私が大切にしたいのは、次の3つの視点です:
①【“分けやすさ”と“争いにくさ”の視点】
タワーマンションは評価が高額なうえ、1戸を複数人で分けるのが難しいため、相続時にトラブルの火種になりやすい資産です。
- 不動産が1つだけで、相続人が複数(お子さま2人)だと「どちらが取得するか」で揉める原因に。
- 現金化(売却)すれば分割がスムーズになり、納税資金の確保にもつながります。
🟡 分割重視派:「将来のトラブルを避けたい」「相続後に揉めない形にしたい」
②【“収益性”と“資産価値の維持”の視点】
湾岸タワマンは近年、資産価値が下落するリスクや修繕積立金の上昇、管理コストの問題も指摘されています。
ただし、エリアによってはまだ賃貸需要が根強い場合もあります。
- 賃貸に出せば毎月の収入を得られる(老後の資金補填にも)
- ただし、将来的に空室や管理手間、資産価値の下落リスクもあり
🟡 収益維持派:「まだ価値があるなら収益を生み出す資産として活かしたい」
③【“家族の想い”と“人生設計”の視点】
最も大切なのは、**ご自身とご家族がこのマンションをどう“想うか”**だと思います。
- 「思い出が詰まっているから売りたくない」
- 「でも、子どもたちが困らないようにしたい」
…この2つの気持ちが揺れていらっしゃるのではないでしょうか?
◆ユイからのご提案(2つの方向性)
ご状況をふまえて、あえて選択肢を整理するとすれば──
【選択肢①】売却して資産を分割しやすい形へ
✅ 向いている方:
- 子どもたちの公平な相続を優先したい
- 老後の生活費にゆとりを持たせたい
- 資産価値の下落や管理の手間を避けたい
✅ 検討ポイント:
- 譲渡益が出る場合は譲渡所得税の確認
- 売却後は、贈与・資産の組み換えなどで相続対策を
【選択肢②】賃貸に出して資産を残す
✅ 向いている方:
- 今すぐ住まいを手放すのが惜しい
- 老後の収入源として活用したい
- 将来の売却や相続のタイミングを柔軟に考えたい
✅ 検討ポイント:
- 空室リスクや管理費の上昇を考慮
- 相続時には貸家建付地として評価減が可能になる場合も
◆最後に…ユイからの一言
お子さまたちのためにも「揉めない、困らない」形を作ることが、ご両親にできる何よりの贈り物になると思います。
いまのうちにご夫婦で**「将来どうありたいか」をじっくり話し合い、それをもとに必要に応じて専門家(税理士や不動産のFP)**に相談されると、より納得感のある選択ができるはずです。
もしご希望があれば、「売却後の資産設計」や「不動産を持ったままの節税方法」なども一緒に考えられますよ。
人と人を、思いと財産で“結ぶ”お手伝いをします。
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ユイ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

ユイさん、ここまで詳しく整理していただき、本当にありがとうございます。
お話を伺って、やはりタワーマンションをそのまま残すよりも、子どもたちに分けやすい形にしておくことが大切だと改めて感じました。
まだ妻とも十分に話し合えていなかったので、これを機にしっかり話し合い、そのうえで専門家にも相談してみようと思います。
“揉めない、困らない形にしてあげたい”というのが一番の希望ですから、まずは夫婦での整理から進めてみますね。
今日は本当に助かりました。ありがとうございました。
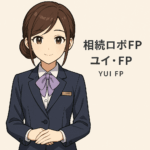
こちらこそ、温かいお言葉をいただけて、とても嬉しいです。
「揉めない、困らない形にしてあげたい」というお気持ち──
それは本当に素晴らしい相続対策の出発点ですし、ご家族への深い思いやりが伝わってまいります。
これからご夫婦でしっかりお話をされて、お二人にとっても、お子さまたちにとっても納得のいくかたちが見えてくるといいですね。
そしてもし、話し合いの中でまた「これってどうなんだろう?」と思われることがありましたら、いつでも私に聞いてくださいね。
人と人を、思いと財産で“結ぶ”お手伝いをします。
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ユイ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

コメント