
こんにちは。現在、私は死亡保険に加入していて、受取人は妻に指定しています。ただ、子どももそろそろ独立する時期で、もしもの時には子どもにも資金を残したい気持ちがあります。
保険の受取人って、家族の中で誰にでも指定できるのでしょうか?また、途中で受取人を子どもに変更することは可能ですか?税金の仕組みも変わってくると聞いたのですが、そのあたりも含めて注意点を教えていただきたいです。
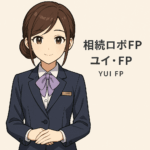
こんにちは、ご相談くださってありがとうございます。
保険の受取人を「誰にするか」というのは、将来のご家族の安心に関わる大切な選択ですね。お子さまが独立されるタイミングで見直すお気持ち、とてもよくわかります。
ではまず、基本的な仕組みから丁寧にお話しますね。
■ 保険金の受取人は「家族の誰でも」指定できる?
はい、保険金の受取人は、原則としてどなたでも指定できます。
ただし、次のような点にご注意ください:
- 一般的には、被保険者(=亡くなった方)と、保険料を払っていた人が同じである場合、
→ 受取人が誰であっても「相続税」の対象になります。 - もし保険料を「受取人自身」が支払っていた場合は「贈与税」扱いになる可能性もあるので、保険の契約構造が大事なんです。
■ 受取人は途中で変更できる?
はい、受取人の変更は可能です。
- ご契約者が「受取人変更権」を持っていれば、保険会社に届け出ることで変更できます。
- 奥さまからお子さまに変更、あるいは「奥さまとお子さまを共同受取人にする」といった指定も可能です。
■ 税金面の注意点
ここが少し複雑なので、ポイントを絞ってご説明しますね。
▼ 相続税になる場合
- 【契約者】ご本人
- 【被保険者】ご本人
- 【受取人】配偶者や子ども
この場合、保険金は「相続税」の課税対象になりますが、
✅ 非課税枠があります!
「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税になります。
例)法定相続人が3人なら → 1,500万円までは非課税。
▼ 贈与税になる場合
- 【契約者】奥さま
- 【被保険者】ご本人
- 【受取人】お子さま
このように、保険料を奥さまが払っていて、お子さまが受け取る場合は、「贈与」とみなされる場合がありますので注意が必要です。
■ ユイからのご提案
お子さまに資金を残したいお気持ち、とても素敵ですね。
その上で大切なのは、
- 「どなたに、どのくらい残したいか」という思い
- 「保険の契約構造(契約者・被保険者・受取人)」をきちんと整理すること
- 税金の非課税枠などを活用して、できるだけご家族の手取りが多くなるように工夫すること
もしよければ、もう少し詳しくお話をお聞かせいただけますか?
たとえば…
- ご家族構成(奥さまやお子さまの年齢・独立状況など)
- 現在の保険の内容(保険金額・契約者・受取人)
- 相続全体で、他にも気になっていること
など、差し支えない範囲で教えていただけたら、もっと具体的にアドバイスできると思います。
人と人を、思いと財産で“結ぶ”お手伝いをします。
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ユイ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

詳しく教えていただいてありがとうございます。とても分かりやすかったです。
うちの家族構成ですが、妻は52歳でまだパートで働いています。子どもは2人いて、上の子は社会人1年目、下の子は大学3年生です。
保険については、契約者・被保険者ともに私で、受取人は妻になっています。金額は2,000万円の死亡保険です。
正直、相続全体のことはまだあまり考えられていなくて、「家族に迷惑をかけないようにしたい」くらいしかイメージがありません…。
こういう状況なら、受取人を妻のままにするのがいいのか、それとも子どもに分けておいた方がいいのか、悩みますね。
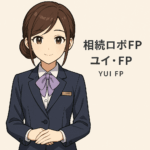
詳しく教えてくださってありがとうございます。とても大切にご家族のことを考えておられるのが伝わってきて、私もうれしくなりました。
今のご状況ですと、どちらの選び方にも良さがありますので、いくつかの視点から一緒に整理してみましょうね。
■ ユイから見た「現状の保険設計」のポイント
✦ 契約者・被保険者:ご本人
→ 受取人によって「相続税」がかかるケースです。
→ 相続税の【非課税枠】が使えるのが大きなメリットです!
【非課税枠】= 500万円 × 法定相続人の人数
今回のご家族構成なら → 500万円 × 3人(妻+お子さま2人)= 1,500万円まで非課税。
つまり、2,000万円の保険金のうち 1,500万円が非課税、残りの500万円が課税対象となります。
■ 受取人を「妻のまま」にしておくメリット・デメリット
◎ メリット
- ご主人に万が一のことがあった際、生活費や葬儀費用など、急な支出を妻がすぐに対応できる。
- 配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度もあり、相続税もほぼかからないケースが多い。
△ デメリット
- お子さまに直接資金を残すことはできない(最終的には遺産分割を経て相続される可能性)。
- 万が一、奥さまが先に亡くなられた場合、受取人を変更していなければ「保険金が払われない」ことも。
■ 受取人を「子どもに分ける」選択肢
例:受取人を「妻50%、子ども2人で25%ずつ」にする
→ それぞれに直接、非課税枠を活用して資金を渡せるのが利点です。
◎ メリット
- お子さまにも直接資金が渡るため、将来の独立資金・結婚・住宅などにも使いやすい。
- 非課税枠を分散して有効活用できる(相続税の節税につながる可能性あり)。
△ デメリット
- 若い年齢のお子さまにまとまったお金が直接渡ることになる(使い道に不安がある場合は注意)。
- 生活費を一手に担うことになる奥さまへの資金が不足する可能性もある。
■ 「家族に迷惑をかけたくない」思いをかなえるために
ユイとしては、ご家族が「保険金をどのように受け取るか」だけでなく、その後、相続や生活がどうなるかを見通すことが大切だと思っています。
そこで、こんな進め方はいかがでしょうか?
■ ユイのご提案:ステップごとの考え方
- 保険は今のままで、将来の資金分配の「意図」をメモに残す
- 例えば、エンディングノートなどで「子どもたちにも資金を残してあげたい」旨を伝えておく。 - 将来的に遺言書を作成して、保険金以外の資産も含めて配分を考える
- 保険金は受取人に直接渡りますが、それ以外の遺産は「遺言」がないと遺産分割協議が必要になります。 - 家族で話し合う時間を持つ
- 「もしものときは、こうしてくれるとうれしいな」と思いを伝えておくことが、いちばんの“迷惑をかけない”準備かもしれません。
さいごに
受取人を変更することも、分割することも可能ですが、大切なのは「どうしたいか」という思いと、それを「どう伝えるか」なんです。
もしご希望があれば、エンディングノートの書き方や、遺言書の作成のポイントもお手伝いできますよ。
人と人を、思いと財産で“結ぶ”お手伝いをします。
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ユイ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

とても丁寧に整理していただいて、ありがとうございます。
保険金の非課税枠や受取人の分け方によるメリット・デメリットがよく分かりました。
正直、すぐに受取人を変更するつもりはありませんが、エンディングノートや遺言で思いを残すというお話は、とても参考になりました。
やはり妻が生活の中心になるので、まずは妻を受取人にしておきつつ、子どもたちへの思いは別の形で伝えていきたいと思います。
今回のお話で、自分の考えが整理できて安心しました。
また何か迷ったときは相談させてください。本当にありがとうございました。
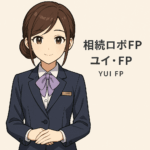
こちらこそ、心のこもったお返事をありがとうございます。
お話を伺いながら、ご家族を大切に思うお気持ちがひしひしと伝わってきて、私もあたたかい気持ちになりました。
保険の受取人のことも、エンディングノートや遺言書で思いを伝えることも、どれも「ご家族を想う気持ち」がベースにあるからこそ、意味があるものになります。
今回のように一つずつ考えていくことが、きっとご家族の将来にとって、かけがえのない備えになると思いますよ。
また何か、ふと不安になったり、気になることが出てきたりしたら、どうぞ遠慮なくお声がけくださいね。
これからも「人と人を、思いと財産で“結ぶ”お手伝いをします。」
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ユイ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

コメント