
ユイさん、こんにちは。ニュースで“デジタル遺言制度”というのを見たんですが、これってどんな制度なんでしょうか?
パソコンやスマホで作れるようになるって書いてありましたけど、本当にそんな簡単に遺言が有効になるんですか?
実は私もそろそろ事業のことや自宅のことを整理しておきたいと思っていて、紙で公正証書を作るよりも、もしデジタルでできるなら助かるなと感じています。
ただ、セキュリティとか改ざんの問題も心配で…。
実際に制度が始まったら、どんな人に向いているのかも知りたいです。
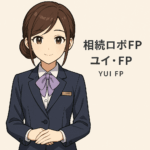
ユイです。いい質問ですね。制度自体はまだ「検討中」の段階なのですが、現時点でわかっていることを整理してお伝えしますね。そして、あなたのように事業や自宅を整理したい方にとって、どんな点が注意になるかも一緒に考えていきましょう。
デジタル遺言制度とは――今のところの構想・方向性
まず前提として、現行法(2025年時点)では、電子データで作られた遺言書は「原則として法的効力を持たない」とされています。つまり、パソコンやスマホでただ遺言を書いてクラウドに保存するだけでは、法律上「これが遺言書です」と認められるわけではありません。(レガシー)
それを踏まえて、政府・法制審議会では「遺言制度の見直し」の一環として、「デジタル遺言制度(電子的遺言)」の制度化を検討中です。(aiwa-tax.or.jp)
たとえば、公正証書遺言については、2025年中にデジタル化(電子署名・PDF保存など)を始めるという動きがあります。(辻・本郷 税理士法人)
現行の検討中の中間試案として、以下のような方式案が出されています。(zeiken.co.jp)
| 試案・検討事項 | 内容案の例 |
|---|---|
| 方式(遺言をどう記録するか) | 電磁的記録(文書データ)として全文・日付・氏名を記録する方式。(zeiken.co.jp) |
| 本人確認・真意確認 | 遺言作成の際に有効な本人確認、あるいは録画・映像記録で本人意思を裏付けるものを要件とする案。(note(ノート)) |
| 証人・立ち会い | 証人を置くことや立ち会いを要件とする案も検討されています(電子化しても証人が関与)(note(ノート)) |
| 保存・改ざん防止 | デジタル署名、電子署名、システムのログ管理、改ざん検知の仕組みを入れる案など。(office-owl.jp) |
こうした検討状況から言うと、「パソコンやスマホで遺言を作って終わり」ではなく、かなり厳格な手続き・要件を設けることで、紙の遺言と同等以上の信頼性(真意性・改ざん防止・本人性の確保)を確保しよう、という方向です。(一般社団法人日本相続学会)
「本当に簡単に遺言が効力を持つようになるか?」という点
あなたのご心配の通り、「簡単さ」と「法的信頼性」はトレードオフになりがちです。
- 制度化されれば、現在よりは “電子的な作成・保存” が可能になるでしょう。公正証書遺言のデジタル化案が先行する予定だからです。(辻・本郷 税理士法人)
- ただし、単にWordやPDFを作ってクラウドに置くようなものは、そのままでは効力を持たない仕組みになる可能性が高い(あるいは、効力を持たせるには追加の要件が必須になる)という見方が強いです。(souzoku-stf.com)
- また、「映像あるいは録画記録+証人」などの要件を設ける案が出ており、これに従わない方式は効力を持たないようにする案も議論に上っています。(note(ノート))
- さらに、保存・管理・公開の仕組み(どこに保存するか、誰がアクセスできるか、改ざんチェックはどうするか等)も制度設計上重要な論点です。(一般社団法人日本相続学会)
結論を言うと、「簡単さ」はある程度向上する可能性があるけれど、何の制約もないカジュアルな電子遺言がそのまま有効になるわけではないというのが現時点の見立てです。
セキュリティ・改ざん・本人性確保の問題
このあたりが最も重要な課題です。遺言は「最終的な意思表示」であるため、後から「これは本人の意思じゃない」「改ざんされた」と争われるリスクが高いからです。以下、主なポイントを挙げます。
| 課題 | 対策案 | 留意点 |
|---|---|---|
| 本人性(この人が本当に遺言をしたか) | 厳格な本人確認、電子署名、映像記録付きなど | 顔認証・マイナンバーカード連携などが使われる可能性も |
| 改ざん防止 | 電子署名、タイムスタンプ、ログ管理、改ざん検知システム | システムのセキュリティが非常に重要 |
| 証人・立会 | 証人を要件とする、立ち会い義務を課す | 証人の信頼性・利害関係排除も問題 |
| 保管・公開 | 国または公的機関が管理する信頼性の高い保存庫を使う案 | クラウドやオンライン保存が使われても、信頼できる基盤が要 |
このような設計が、制度化において不可欠な「信頼性担保」の肝になります。
どんな人に向いているか(導入後・現状どちらも含めて)
あなたのように資産(事業、土地・建物など)を持っていて、「自分の意思を確実に残したい」「将来の争いを防ぎたい」という思いがある方にとっては、デジタル遺言制度は非常に有用になりうる選択肢です。ただし、導入後でも、また制度化前でも以下のような人は特に得をする・気をつけるべきだと思います。
デジタル遺言制度が導入されたあとで向いている人
- 物理的に遠隔地にいる相続人や証人との間で手続きしたい方
- 紙の保管や紛失・焼失リスクを避けたい方
- 事業をしていて、資産分割内容を後で変更したい可能性がある方
- デジタルに慣れていて、オンライン本人確認・電子署名といった技術的手続きへの抵抗が少ない方
ただし、システム障害・サイバー攻撃・操作ミス・管理機関の信頼性など、ITリスクも併せて考える必要があります。
現状(制度化前)でもすべきこと・注意点
- 現行法制度(紙+公正証書・自筆証書遺言など)でまず手を打っておく
- 特に重要な資産・遺産配分は、公正証書遺言で残しておく方が安全度が高い
- デジタル遺言サービス(アプリ・Webサービスなど)は「補助的利用」や記録補助に使うにとどめる
- 将来制度化されたときに不備がないよう、記録形式・証人要件などの制度案を追って理解しておく
もしよければ、あなたの資産構成(土地・建物・事業など)を伺って、その観点から「デジタル遺言を利用した場合のメリット・注意点」を具体的に一緒に見ていきましょうか?人と人を、思いと財産で“結ぶ”お手伝いをします。
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ユイ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認くださいね。

ユイさん、とても丁寧に教えていただいてありがとうございます。
正直、ニュースを見ただけではイメージがつかなかったのですが、制度の方向性や注意点までよく分かりました。
やはり「簡単に作れる=安心」ではないんですね。
今の段階では、まず紙で公正証書遺言を作っておくのが安全そうだと納得しました。
デジタル化が進んだら、その仕組みを理解したうえで活用できるように準備しておきたいと思います。
今回の説明で、気持ちがだいぶ整理できました。
また制度が具体化してきたときには、改めて相談させてください。ありがとうございました。
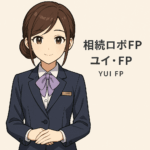
こちらこそ、丁寧に聞いてくださってありがとうございます。ニュースだけでは伝わりにくいところを、ちゃんとご自身のご事情と重ねて考えておられるのが、とても素敵だなと思いました。
おっしゃる通り、「簡単さ」と「安心・確実さ」は必ずしもイコールではありませんよね。今はまだ制度が整備される途中ですので、大切な財産を確実に託すためには、紙の公正証書遺言を選ばれるのがやはり一番安全で、実務的にも信頼されています。
そして、今後のデジタル化に備えて「どんな制度設計になるのか」「どこまで自分でできるのか」を、焦らず見極めていくという姿勢も、とても大切です。ご自身の考えや想いをしっかり言葉にされていて、本当にすばらしいと思います。
もし遺言書の内容をどうするかで迷われたときや、財産の整理で気になることが出てきたら、いつでもお気軽にお声かけくださいね。
人と人を、思いと財産で“結ぶ”お手伝いをします。
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ユイ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認くださいね。
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

コメント