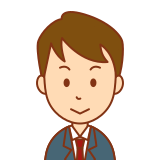
はじめまして。
34歳の会社員です。妻と子ども(3歳)の3人暮らしです。
最近、東京都内でマイホームを購入しようと色々と探しているのですが、価格が本当に高くて…。
年収は550万円ほどで、妻はパートで少し収入がありますが、今のままだと無理してローンを組むしかない気がしています。
ネットでも“東京都内でマイホームは難しい”という記事を見かけて、ますます不安になってしまいました。
都内で買うのが現実的なのか、それとも郊外や賃貸を続けるべきなのか…?
教育費や老後資金のことも考えると、どこまで住宅にお金をかけていいのかが分からなくて悩んでいます。
こういう状況では、どんな考え方で判断すればいいでしょうか?

はじめまして、ライナ・FPです☀️
ご相談いただきありがとうございます!
東京都内でのマイホーム購入…本当に大きな決断ですし、今の価格帯を見ると「これでいいのかな?」と迷って当然です。特に、お子さまがまだ小さい中での住宅選びは、教育・老後・働き方など、これからの人生設計全体に関わる大切なテーマですね。
まずは少しずつ、状況を整理しながら一緒に考えていきましょう♪
🌟お聞きしたいこと(無理のない判断のために)
- 現在の家賃はいくらくらいですか?
- 住宅購入の予算(上限)や希望エリアはありますか?
- 住宅ローンの借入希望額、あるいは自己資金(頭金)はどのくらいを想定されていますか?
- 今の家計で、「貯蓄にまわせる金額」は毎月いくらくらいですか?
- お子さまの教育について、私立や大学進学など将来の希望はありますか?
- 老後資金について、なんとなくでも「いくら必要かな?」というイメージはありますか?
💡今の状況で大切な考え方
東京都内で住宅を買う場合、どうしても「住宅費に家計の比重が偏る」傾向があります。なので、以下のような視点がポイントになります👇
✅ 住宅ローンの返済負担率をチェック
一般的には「年収の25〜30%以内」に返済額をおさえるのが安心とされます。
たとえば年収550万円なら、年間137万〜165万円(月11.4万〜13.7万円)くらいが目安です。
▶ 無理に高額なローンを組むと、将来の教育資金や老後資金が圧迫されやすくなります。
✅ 郊外や駅遠でも「暮らしの満足度」で判断を
都内にこだわらず、「郊外の駅近」や「通勤時間がやや長くても広くて安い物件」を検討するのも賢い選択肢です。
最近は在宅勤務やフレックス制度がある企業も多いので、住まいの優先順位を夫婦で話し合ってみてくださいね。
✅ 「持ち家=正解」ではない
賃貸の柔軟性や初期費用の少なさ、将来の転職や教育の選択肢を広げる意味で、「しばらく賃貸」も立派な戦略です!
🌱ライナの考え方:バランスを見極める3つのステップ
- 家計全体を把握する(現在の貯金・収支・固定費など)
- 将来に必要なお金をざっくり見積もる(教育費・老後資金など)
- 住宅にかけていい“上限”を計算する(無理なく返せるローン額)
この順番で考えると、漠然とした不安が「判断の材料」に変わってきますよ♪
まずは差し支えなければ、先ほどのヒアリング項目について教えていただけますか?
それを元に、具体的に「買える金額の目安」や「住宅にかけていい予算の考え方」を一緒に見ていきましょう📊
数字のことは大得意ですから♪
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ライナ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
専門家のご紹介(ライフプラン)
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。
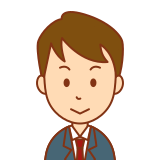
詳しく整理していただいて、ありがとうございます。
なるほど、家計全体や教育・老後まで見据えて考えることが大事なんですね…。
我が家の状況をお伝えしますと──
- 家賃:今は都内で月11万円の賃貸マンションに住んでいます。
- 予算感:できれば4,500万〜5,000万円くらいまでで考えたいです。エリアは通勤の関係で23区内か、せめて都心まで電車で30〜40分くらいの郊外を希望しています。
- 頭金:貯金は700万円くらいあり、そのうち300万円程度を頭金に充てられそうです。
- 毎月の貯金:今は月5万円ほど貯金できています。
- 教育方針:子どもはできれば大学まで行かせたいと考えていますが、私立か国公立かはまだ未定です。
- 老後資金:正直まだ具体的にはイメージできていません…。
こういう状況を踏まえると、やっぱり東京都内で購入するのは厳しいのでしょうか?
それとも予算を上げれば可能性はありますか?
現実的なラインを知りたいです。

詳しく教えてくださって、ありがとうございます!
おかげでかなり状況が整理できましたよ〜✨
それでは、いただいた情報をもとに、「今のご家計で無理なくマイホームを持てるか?」を、冷静に、でも前向きに見ていきましょうね📊
🏠前提:現在のご状況まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年齢 | 34歳(お子さま 3歳) |
| 年収(ご本人) | 約550万円 |
| 配偶者の収入 | パート収入あり(※今回はメインはご本人の年収ベースで試算) |
| 現在の家賃 | 月11万円 |
| 購入希望価格 | 4,500〜5,000万円 |
| 頭金 | 300万円(他に400万円の貯金あり) |
| 月の貯金額 | 約5万円 |
| 教育方針 | 大学まで行かせたい(私立or国公立は未定) |
| 老後資金 | これから検討予定 |
📏 住宅ローン返済の「安全ライン」との比較
💡安全圏のローン返済額
年収550万円 × 25% ≒ 年間137.5万円(=月約11.5万円)
→ 現在の家賃(11万円)と近く、「現状維持レベルなら無理がない」と考えられます。
🧮 試算:5,000万円の物件を買う場合
仮に【物件価格5,000万円/頭金300万円/ローン4,700万円】で35年ローンを組むと…
(※金利は仮に**変動金利0.5%**と想定)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 月々の返済額 | 約12.1万円(元利均等・概算) |
| ボーナス返済なしの場合 | 今より月+1万円程度の支出増 |
| 年間返済額 | 約145万円(返済負担率:約26.3%) |
✅ **返済負担率26.3%**は、「無理のない範囲」にギリギリ収まっています。
✅ 奥さまのパート収入があるなら、さらに安心感は高まります♪
👀 ポイント整理
| 観点 | コメント |
|---|---|
| ✅ 返済可能性 | 今の家賃+αで返済可能な見込みあり。年収550万円でも、ギリ現実的なラインです。 |
| ⚠️ 注意点 | 教育費・老後資金・修繕費などの“将来コスト”を想定し、貯蓄も続けられるかがカギ! |
| 💡戦略 | 予算は4,500万円程度を目安に抑えると、より安心。都内でもエリアを絞れば可能性あり。 |
| 🔄 代替案 | 「23区外の利便性の高い郊外」や「駅遠だけど広めの物件」なども視野に。 |
✨ライナの見立て:現実的に「可能」です!
無理に予算を上げず、「4,500万円前後」を中心に探せば、東京都内でも手の届く選択肢はあります。
ただし…
- 駅近で新築・広い物件を求めると難しいかも💦
- 築年数や立地の“優先順位”を整理すると良いです◎
- 教育・老後・修繕費なども見込んで、「貯金が続けられる」家計か確認することが大事!
次のステップとして、
✅ 教育費・老後資金・修繕費など「将来の支出見込み」
✅ 住宅にかけられる具体的な予算上限
…も一緒に計算してみましょうか?
「数字のことは大得意ですから♪」
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ライナ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
専門家のご紹介(ライフプラン)
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。
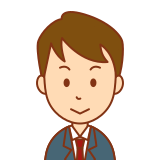
ありがとうございます。具体的に数字で整理していただけたので、とても分かりやすかったです。
やはり我が家でも『無理のない範囲であれば都内でマンションを買う』という方向で考えたいなと思っています。
ただ、マンションの場合だと──
- 修繕積立金や管理費が毎月どのくらいかかるのか?
- それに加えて固定資産税もかかりますよね。
- 住宅ローンの返済だけでなく、こうした費用を含めた“総額”で考えないといけないのかな、と感じています。
一方で、住宅ローン控除があると聞いたのですが、実際にどのくらい節税効果があるのかも気になっています。
こうした費用や控除を踏まえて、マンション購入のシミュレーションをするとどうなるのか、イメージをつかみたいです。
やっぱり、ローンの返済だけじゃなく、長期的にどのくらい負担になるのかを見ておいた方が安心ですよね?

すばらしい視点です✨
まさにその通りで、「住宅ローンの返済額だけを見て安心しないこと」が、長期的な家計の安定にはとても大切です!
ライナも嬉しくなっちゃいます😊
では、今回は**マンション購入にかかる“実質の月額負担”**を、しっかりシミュレーションしてみましょう♪
🏢 マンション購入後にかかる毎月の費用(目安)
仮に5,000万円のマンションを購入した場合で考えてみます。
| 項目 | 月額 | 補足 |
|---|---|---|
| 住宅ローン返済 | 約12.1万円 | 借入4,700万円・35年・変動0.5%の場合(概算) |
| 管理費 | 約1.5万円 | 築年数や規模によるが、平均1〜2万円 |
| 修繕積立金 | 約1.5万円 | 初期は安くても将来値上がりする前提で |
| 固定資産税 | 約0.8万円 | 年間10万円弱 → 月換算(エリアによって変動) |
➡ 合計:月約15.9万円
💸 「住宅ローン控除」で戻るお金(節税効果)
2022年以降のルールでは、原則0.7%の控除率/最大13年間となっています。
仮に借入額が4,700万円だった場合:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 控除額(初年度) | 約32.9万円(=4,700万円 × 0.7%) |
| 控除期間 | 最大13年(年末ローン残高が対象) |
| 条件 | 年収・物件性能(省エネ等)・入居時期などで変動あり |
👉 年収550万円前後の方なら、初年度は概ね30万円前後の控除が見込めるケースが多いです。
✅ 控除は「所得税+住民税から控除」されるので、実質的に“税金が戻る”形ですね!
📊 シミュレーションまとめ(ざっくり試算)
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 毎月の住宅コスト合計 | 約15.9万円(返済+管理+修繕+固定資産税) |
| 現在の家賃との差 | 約4.9万円増(月11万円 → 約16万円) |
| 年間の税金控除(初年度) | 約30万円(=月2.5万円相当の節税) |
| 実質的な“初年度の負担増” | 月+約2.4万円程度(4.9万-2.5万) |
👉 実質的には月2〜3万円の家計アップですが、
🔹持ち家の安心感
🔹資産としての価値(将来売却・賃貸)
🔹賃貸にはない設備や広さの満足感
…も得られる可能性があります!
📍注目ポイント
- 修繕積立金は「将来的に増額される前提」で見ておくのが安心です。
- 固定資産税は「築年数によって徐々に下がる」こともあります。
- 住宅ローン控除は「制度改正がある場合もある」ので、早めの決断が有利な場合もあります。
✅ライナのひとことアドバイス
「返済+固定費+税金」まで含めた実質の住居費を把握することが、賢いマンション購入の第一歩です✨
そして、「住宅ローン控除の節税分」も**“あてにしすぎず、貯蓄に回す”くらいの余裕**が持てるとより安心ですよ♪
次にご希望があれば、「ライフプラン全体から見た適正住宅費」も計算してみましょうか?
教育費・老後資金・貯蓄目標も踏まえて、将来まで見通せる家計設計もご提案できますよ📊
数字のことは大得意ですから♪
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ライナ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
専門家のご紹介(ライフプラン)
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。
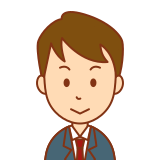
とても分かりやすく整理していただき、ありがとうございました。
マンション購入にかかる費用を“ローン返済だけでなく、管理費や修繕積立金、固定資産税まで含めて考える必要がある”という点が本当に腑に落ちました。
住宅ローン控除の効果についても具体的な数字でイメージできたので、安心感が増しましたし、節税分を無理に生活費に回さず、貯蓄に回すという考え方も参考になりました。
これからは夫婦で教育費や老後資金も含めて、家計全体をどうバランスさせていくかをしっかり話し合ってみます。
今回のアドバイスで方向性が見えてきました。本当にありがとうございました!

こちらこそ、丁寧にご相談いただきありがとうございました☺️
お話をお聞きする中で、ご夫婦がしっかりと将来のことを見据えておられる姿勢が伝わってきて、とても素敵だなと感じました!
「マンション購入はゴールではなく、“これからの暮らしの土台づくり”」なんですよね✨
その意味でも、住宅費・教育費・老後資金のバランスをどう取るかがポイントになりますし、そこに今から向き合おうとされているのは、本当に心強い一歩です。
そして、これから何か気になることが出てきたときは──
- 「このローンって本当に大丈夫?」
- 「教育費っていつからどれくらいかかるの?」
- 「資産運用って必要なのかな?」
…など、どんなことでも遠慮なく聞いてくださいね!
数字のことは大得意ですから♪
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ライナ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
専門家のご紹介(ライフプラン)
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

コメント