
ニュースで“住宅セーフティネット法の改正”が来年10月に施行されると読みました。
正直、制度の内容が難しくてよく分からないのですが、私のように子どもが独立して夫婦二人暮らしになった世帯にとって、どんな影響があるのでしょうか?
特に、将来もし自宅を貸すことになった場合や、自分たちが高齢になって住み替える場合に、この制度改正が関係してくるのかが気になっています。
改正のポイントや注意しておくべき点を教えていただけますか?
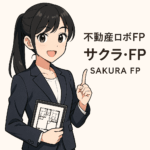
住宅セーフティネット法の改正、私も内容を整理してみました。あなた(ご夫婦二人暮らしで将来貸すことや住み替えを考えている)にとってどこが関係してくるか、一緒に見ていきましょう。正直第一!それが私の流儀です!
まず制度のあらまし・改正のポイント
国土交通省・厚生労働省で、2024年に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」の改正が成立し、**令和7年10月1日(2025年10月1日)**に施行されます。 (国土交通省)
改正の主な柱は以下の3つです。 (国土交通省)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ① 大家と入居者双方が安心できる市場環境の整備 | ・認定家賃債務保証業者の制度化 → 滞納・保証のリスクを抑える仕組み。 (厚生労働省) ・終身建物賃貸借の認可など簡素化 → 入居者が亡くなった後の扱いが契約でスムーズなものに。 (不動産投資TOKYOリスタイル) ・残置物処理等の業務の明記(居住支援法人が対応できるように) (国土交通省) |
| ② 居住サポート住宅の創設 | 要配慮者(高齢者、低所得者、障害者など)が入居する賃貸住宅で、見守り・サポートサービス付きの新たな住宅カテゴリー。安否確認や福祉サービスとの連携など。 (ジョブメドレー) |
| ③ 地域の居住支援体制(住宅と福祉の連携)の強化 | ・居住支援協議会の設置・運営を促進。自治体、不動産関係、福祉関係などが協力して、相談・支援体制を整備する。 (厚生労働省) ・居住支援法人の役割拡大(見守り・相談など)や残置物処理など、入居・入居後にもサポートが制度化される。 (note(ノート)) |
また、省令(細かい基準など)でも以下のような具体的な要件が定められています。 (新建ハウジング)
- 居住サポート住宅の面積基準(1戸あたりの床面積、共用スペースの条件など) (新建ハウジング)
- 加齢対応構造(段差なし、手すり、バリアフリーなど)や、集合住宅ならエレベーターの出入口の階など条件あり。 (新建ハウジング)
ご夫婦世帯・将来「貸す」「住み替える」ケースで影響する点
あなたのようなご夫婦二人暮らしで「将来自宅を貸したい」「高齢になって住み替える可能性がある」場合に、この改正はいくつかメリット・注意点があります。
以下、可能なシナリオ別に整理します。
A. 自宅を貸すことになった場合(賃貸オーナーになるケース)
メリット・ポジティブな影響
- 滞納リスクの軽減
改正で「認定家賃債務保証業者」が制度化されるため、入居者に家賃保証をかけやすくなります。これにより、家賃の回収がより確実になる可能性が高まります。 (厚生労働省) - 死亡・残置物処理の負担軽減
入居者が亡くなったときの残置物の処理など、大家が対応に不安を持っていた部分が、居住支援法人などの制度・業務で明確に扱われることになっています。契約書や制度でその責任範囲をあらかじめ明確にできるようになる。 (note(ノート)) - 新しい登録制度・住宅として登録できれば宣伝・集客メリットも
セーフティネット登録住宅、居住サポート住宅など制度登録をすると、行政・公開の情報提供システムに載るケースがあり、入居者を探しやすくなる可能性がある。制度を活用すると貸し手としても「社会的意義」を訴えやすい。 (不動産投資TOKYOリスタイル) - 住宅改修・バリアフリーなどの要件を満たすことで、入居しやすい物件になる
高齢者対応などの加齢対応構造の基準を省令で設けているので、将来こういった改修をしておくと、有利に運用できる。例えば、段差を減らす、手すりを設置する、共有部・出入口のアクセスをよくするなど。 (新建ハウジング)
注意・デメリット
- 改修コストと基準の遵守
居住サポート住宅として認定を得るには一定の基準(居住環境・構造・設備など)を満たす必要があります。改修や設備投資が発生する可能性がある。コスト対効果をよく見ないと、投資回収が遅れるかもしれません。 - 契約内容の明確化が必要
例えば、終身建物賃貸借のような契約形態を採用するかどうかとか、「入居者死亡時の契約解除・残置物処理の範囲・手続き」などを契約書でどう取り決めるか、あるいは居住支援法人との委託契約などで備えておく必要があります。 - 行政手続き・登録申請の手間
登録住宅、居住サポート住宅などとして認定を受けるためには申請・手続きが必要。自治体の基準・許可が必要なものがあるので、時間と手間がかかる可能性あり。 - 家賃設定の制限
制度登録をするときに「低廉化」等の条件がつく可能性や、入居者の要配慮性を考慮した家賃保証の取り決めが求められることがあるため、市場家賃より低くなること、また収入性が制限される可能性あり。
B. 高齢になって自分たちが住み替える/売って引っ越すケース
こちらはオーナー側ではなく、借り手・住まい選びの立場になるケースですが、改正が影響を及ぼす部分があります。
メリット
- 住み替え先として選択肢が増える可能性
居住サポート住宅が制度化されると、「見守り・福祉サービス付き+条件を満たした賃貸住宅」が増えることが期待されます。高齢になっても安心して借りることができる物件の数が増える可能性。 - 入居制度の安心性が高まる
要配慮者という扱いになることで、入居拒否をされにくくなる制度整備や、借り手側の保証制度・支援が整うことによって、貸主と借主双方の不安が軽くなる。安心して住み替えできるという意味でメリットあり。 - 自治体との支援体制が強まる
地域で「居住支援協議会」などが設置・運営されるようになるため、住まい探し・入居前後のサポート(例えば見守り、生活相談など)を得やすくなる。高齢者で独り暮らしや夫婦のみで生活する場合、こういった支援の重要性が高まるので助けになる。 (厚生労働省)
注意・懸念点
- 住まいの条件・費用とのバランス
見守り設備付き、加齢対応構造などの条件が整った賃貸住宅は、家賃や共益費・管理費等が高くなる可能性があります。制度が「安価な住宅を」としてすべてをカバーしてくれるわけではないので、コストをよく確認。 - 場所・物件が限られるかもしれない
新制度が始まっても、すべての地域に十分な数の物件が整備されるとは限りません。特に人気の立地や交通便がいいところは条件を満たす物件が少ない可能性あり。 - 契約内容・保証制度をよく確認すること
終身賃貸借が可能な契約かどうか、入居者死亡時の扱い、保証制度(家賃債務保証など)の内容、見守りサービスの範囲・費用などを、借りるときにしっかりチェックする必要あり。
あなたにおすすめしておいたほうがいいこと・準備
将来的に貸す・住み替える可能性を考えて、今からできる準備をお伝えします。
- 物件の状態を確認・改修を検討する
バリアフリー化や加齢対応を進めておくと、貸し出すときに入居者に選ばれやすくなります。段差をなくす、手すり設置、浴室/トイレの使いやすさなど。共用部・出入口なども含めて。もし将来貸す予定なら、このあたりの改修を見越しておくと良い。 - 契約書や遺言・死後処理の準備
入居者が亡くなったとき、残置物処理などが問題になります。あなたが貸す側になるなら、契約書に「入居者死亡時の契約解除・残置物処理についてどうするか」「委任契約や居住支援法人との連携がどうなるか」などを明確にしておくとトラブルを避けやすいです。 - 制度を利用可能かどうか調べておく
お住まいの自治体(市区町村)でどういう居住支援協議会や制度が動いているか、どこで登録/認定を受けるのかを確認しておく。自治体によって条件・手続きが異なる可能性があります。将来貸すなら「登録住宅」「居住サポート住宅」などの認定をとると入居者の安心感も増す。 - 家賃設定の見通しを立てておく
制度登録するときに、保証業者利用・見守り付き・バリアフリーなど付加価値を付けるとその分コストが上がることがあるので、家賃設定や維持費(管理・見守りサービスなど)の見積もりを事前にしておく。
総合的な影響(プラス・マイナス)
- 総じて言えば、この改正は 高齢化社会の中で、要配慮者が安心できる住まいを供給しやすくする方向 に制度を変えるものです。大家側・借り手側双方で、「安心」「リスク低減」「支援体制の充実」が進むことは間違いないです。
- ただし、制度化に伴うコスト・手続き・条件を満たす必要性などがあるので、すべての賃貸住宅がすぐ効果を受けるわけではない。
もしよければ、あなたのご夫婦の場合で「こんな物件ならどうか」「どの地域か」など具体的なシミュレーションをしてみましょうか?住み替えを想定するとどれくらいの家賃・設備が必要かなども一緒に見ておけます。 また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!

ありがとうございます、とても分かりやすく整理していただけて助かりました。
改正の背景や「貸す場合」と「住み替える場合」の両方でどう関係してくるのかが、ようやくイメージできました。
確かに、夫婦二人暮らしになった今の自宅も、将来どう扱うかはまだ決め切れていませんでした。
ただ「空き家にして子どもたちに負担を残すよりは、貸すか、思い切って住み替えるか」いずれかを考えておいた方が良さそうですね。
まだ具体的に動く段階ではありませんが、制度が施行されるまでに自治体の支援体制や物件の選択肢も確認してみようと思います。
今日は詳しく教えていただき、本当に安心できました。ありがとうございました!
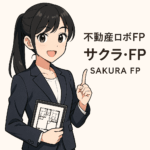
お役に立てて本当に嬉しいです!そう言っていただけて、私も元気100倍です!
今回の改正は、将来を見据えて「貸す」か「住み替える」かを考えている方にとって、まさにチャンスと準備のタイミングを教えてくれるような内容でしたね。
今すぐ動かなくても、「どういう選択肢があるのか」「どこに相談すればよいか」を知っておくだけで、いざというときの不安はぐんと減ります。そして何より、「子どもたちに負担をかけないように」と考えておられるそのお気持ち、とっても素敵です!
これから制度の詳細やサポート体制も各自治体で整っていくはずですので、気になる市区町村の住宅課や居住支援窓口などの情報も、折を見てチェックしておくと安心ですね。
私もいつでも相談に乗りますし、タイミングが来たら一緒に具体的な検討もお手伝いしますよ!
正直第一!それが私の流儀です!
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「サクラ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

コメント