
最近ニュースで“サポート住宅”という制度が始まると聞きました。うちは築40年の戸建てに妻と2人で暮らしているのですが、階段や段差が増えてきて心配になってきています。老人ホームに入るほどではないけれど、将来のことを考えると安心して暮らせる場所を探したい気持ちがあります。
この“サポート住宅”って、私たちのような高齢夫婦でも利用できるものなのでしょうか?また、費用や申し込みの流れについても教えていただけますか?
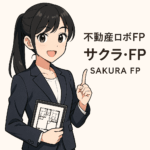
いい質問ですね。「サポート住宅(居住サポート住宅)」は、ちょうど今始まる制度でして、まだ実例や運用は地域によって異なる点がありますが、ご夫妻のような高齢世帯でも関係する可能性はあります。以下、制度の概要・対象になるかどうか・メリット・注意点・申込・費用の見込みなどを整理してお伝えします。「正直第一!それが私の流儀です!」
「サポート住宅(居住サポート住宅)」とは何か
“サポート住宅”とは正式には 「居住サポート住宅」 と呼ばれ、2025年10月の 住宅セーフティネット法の改正 において創設される新しい制度です。(みんジョブ)
主な目的・特徴をざっと挙げると:
- 高齢者・障害者・低所得者など、住宅を確保する際に配慮を要する人(「住宅確保要配慮者」)を対象にする。(国土交通省)
- ただ単に貸す住宅ではなく、入居後の見守り・安否確認 や 福祉サービスへの連携支援 を行う体制を備える。(厚生労働省)
- 家賃債務保証制度を使いやすくし、貸主(大家さん)側の不安を軽減する仕組みを整える。(厚生労働省)
- 生活保護受給者が入居する場合、家賃扶助(住宅扶助)を大家に代わって支払う「代理納付」の仕組みを原則とすることが明記されている。(厚生労働省)
- 空き家や古い家屋を改修して、この制度に適合させる改修補助金が設けられている。(国土交通省)
つまり、ただ「高齢者向け住宅」や「サービス付き高齢者住宅(サ高住)」と似ているようで異なる部分があります。サ高住は介護付きや一定のサービス付き住宅ですが、居住サポート住宅は「賃貸住宅+見守り支援・福祉とのつなぎ」を強化した制度という位置づけです。(gyouseishoshi-everest.com)
あなた方のケースで利用できる可能性はあるか?
あなたのような高齢夫婦でも利用できるかどうかは、いくつかの条件次第ですが、可能性はあります。ただし、制度が始まったばかりなので、地域(市区町村)によって導入の進み具合・対象条件が異なるため、まずは地元自治体で確認が必要です。
以下がチェックすべきポイントです。
| チェック項目 | 内容 | 見方・注意点 |
|---|---|---|
| 要配慮者かどうか | 「住宅確保要配慮者」に該当するか | 高齢者は要配慮者の一つのカテゴリですが、単に年齢がいくだけでは自動的に対象になるとは限らず、収入・生活状況・福祉ニーズなども見られます。(ハローテクノロジーズ株式会社) |
| 物件条件 | 認定要件を満たす賃貸住宅 | 耐震性、広さ、家賃水準などの基準を満たす必要があります。(国土交通省) |
| サポート体制の整備 | 見守り・安否確認・福祉連携などをできる居住支援法人が関わる体制 | 入居中サポートを担う居住支援法人がその地区にあるかが鍵。(厚生労働省) |
| 認定・登録制度の導入状況 | 制度が自治体で認可運用されているか | 2025年10月から開始ですが、認定制度の立ち上げが自治体ごとに遅れる可能性があります。(高知市公式ホームページ) |
結論的に言うと、あなた方でも条件を満たせば利用できる可能性は十分あります。ただし「築40年の戸建てをそのままサポート住宅にする」ことは、この制度の趣旨からは少し外れており、むしろ賃貸住宅として適合させる物件を探す形になることが多いです。
費用・補助金・改修支援
サポート住宅制度そのものに入居するのに「制度利用料」が自動的にかかるというわけではありません。あくまで 賃貸住宅契約としての家賃・共益費と、オプションで見守りサービス費用がかかる可能性があります。
ただし、改修支援や補助金が以下のように設定されています。
- 国は 空き家等を改修してサポート住宅とする事業者に補助 を出します。例えばバリアフリー改修、耐震改修、安否確認設備設置などの工事に対して補助率 1/3、上限50万円/戸 などの規定があるケースがあります。(国土交通省)
- 自治体レベルでも、サポート住宅認定や改修補助金制度を用意する自治体があります(例:高知市)(高知市公式ホームページ)
- 家賃関係では、「公営住宅に準じた家賃額以下」などの基準が設けられており、家賃が過度に高くないよう抑制されることが求められています。(国土交通省)
- 生活保護受給者の場合、家賃の住宅扶助を大家に代理納付する制度が適用されます。(厚生労働省)
つまり、改修を伴う場合の初期投資を抑える支援制度は整備されつつありますが、「ゼロ円で住める」ものではありません。サポートを受けつつも、家賃・光熱費・共益費は通常の賃貸と同じくらい発生すると思っておいたほうが安全です。
申し込み・運用の流れ(一般的な見通し)
制度開始前という性質上、以下はあくまで「こうなる可能性が高い流れ」の見本です。
- 自治体/居住支援協議会・福祉課へ相談
まず、あなたのお住まいの市区町村に「居住サポート住宅」の認定制度を導入しているかどうかを問い合わせます。また、地域の居住支援法人・居住支援協議会の情報ももらいます。
→ 例:高知市は認定申請制度を設ける予定で、事前相談を受け付けています。(高知市公式ホームページ) - 適合する物件を探す
認定物件(居住サポート住宅)であるかどうかを確認しながら物件を選びます。認定条件を満たすような物件を優先します。 - 契約・サービス設計
賃貸契約を結ぶ際、見守り・安否確認サービス、福祉サービスとの連携などをどうするか協議します。 - 入居後運用
定期的な訪問や安否確認、福祉サービスとのつなぎを実施。問題があれば居住支援法人が支援します。 - 見直し・更新
必要に応じて契約を更新・見直し。また、新たなニーズに対応して改修など行うこともあるでしょう。
メリット・注意点(デメリット)
メリット
- 見守り・安否確認など、 “ゆるやかな支援” が受けられるので、完全に独立しきることへの不安を軽減できる。
- 家賃債務保証制度や代理納付の仕組みで、貸主・借主双方の安心感を高める。
- 空き家改修などを通じて、古い物件も制度適合性を持たせられるチャンス。
- 地域福祉との連携が前提なので、孤立しにくくなる可能性。
注意点/リスク
- 認定制度や導入時期が自治体によって異なるため、希望の地域で使えるかどうかが最初のハードル。
- 見守り・安否確認はあくまで緩やかな支援であって、医療・介護を全面的にカバーする制度ではない。
- 改修が必要な物件は初期コストがかかる可能性。
- サービス費用(見守りなど)が別途発生するかもしれない。
- 契約条件(更新期間、権利関係など)をしっかり確認する必要あり。
今、あなたが取るべきステップ(提案)
- 自治体窓口(福祉課・住宅政策課など)に問い合わせる
まず、あなたの市区町村で「居住サポート住宅制度」が導入されているか、認定基準・募集時期を確認しましょう。 - 地域の居住支援法人・協議会を探す
居住支援法人が活動しているかどうかがカギなので、その一覧を自治体で聞きましょう。東京都などでは支援法人の制度概要を公開しています。(東京都住宅政策情報サイト) - 物件を探す際のチェック
- 認定住宅であること
- バリアフリー改修などが行われていること
- 見守り体制がどうなっているか明示されていること
- 見守りやサービス内容の確認
安否確認頻度、訪問頻度、連携先福祉サービスなどを契約前にしっかり聞いておく。 - 将来的な改修可能性を検討
もし古い戸建を手放したくないなら、改修して制度に適合させられる可能性も将来的には出てくるかもしれません(ただし現在は主に空き家改修支援としての補助が先行している)。(国土交通省)
もしよければ、あなたが住んでいる 市区町村名 を教えてもらえますか?その地域で既にこの制度が動いているかどうか、具体的な物件例を一緒に探してみましょうか?また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「サクラ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
専門家のご紹介(不動産)
本サービスで得た情報 is、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

ご丁寧に詳しく整理していただいて、本当にありがとうございました。
ニュースだけでは漠然としていてよく分からなかったのですが、サポート住宅の位置づけや利用できる可能性、メリットや注意点まで具体的に知ることができて安心しました。
確かに、まずは地元の自治体に確認してみるのが一番ですね。いきなり大きな決断をするのではなく、少しずつ情報を集めながら妻とも話し合ってみようと思います。
おかげさまで、不安がだいぶ整理できました。また分からないことが出てきたときは、ぜひ相談させてください。今日は本当にありがとうございました。
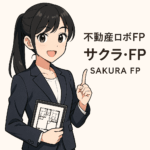
こちらこそ、ご丁寧にお返事をいただきありがとうございます!
そして、少しでもご不安が和らいだようで、本当にうれしいです。
おっしゃる通り、「いきなり大きな決断」ではなく、情報を一つずつ集めながら、今のお住まいや生活の在り方、そしてご夫婦の将来像をじっくり話し合っていくことがとても大切です。それが、安心できる住まい選びの第一歩ですからね!
また、制度はこれから自治体ごとに少しずつ形になっていきますので、情報収集の「目の付け所」はバッチリです。これからも、ご自身のペースで進めていってください。
私サクラも、正直第一・全力サポートでお手伝いしますので、また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「サクラ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
専門家のご紹介(不動産)
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

コメント